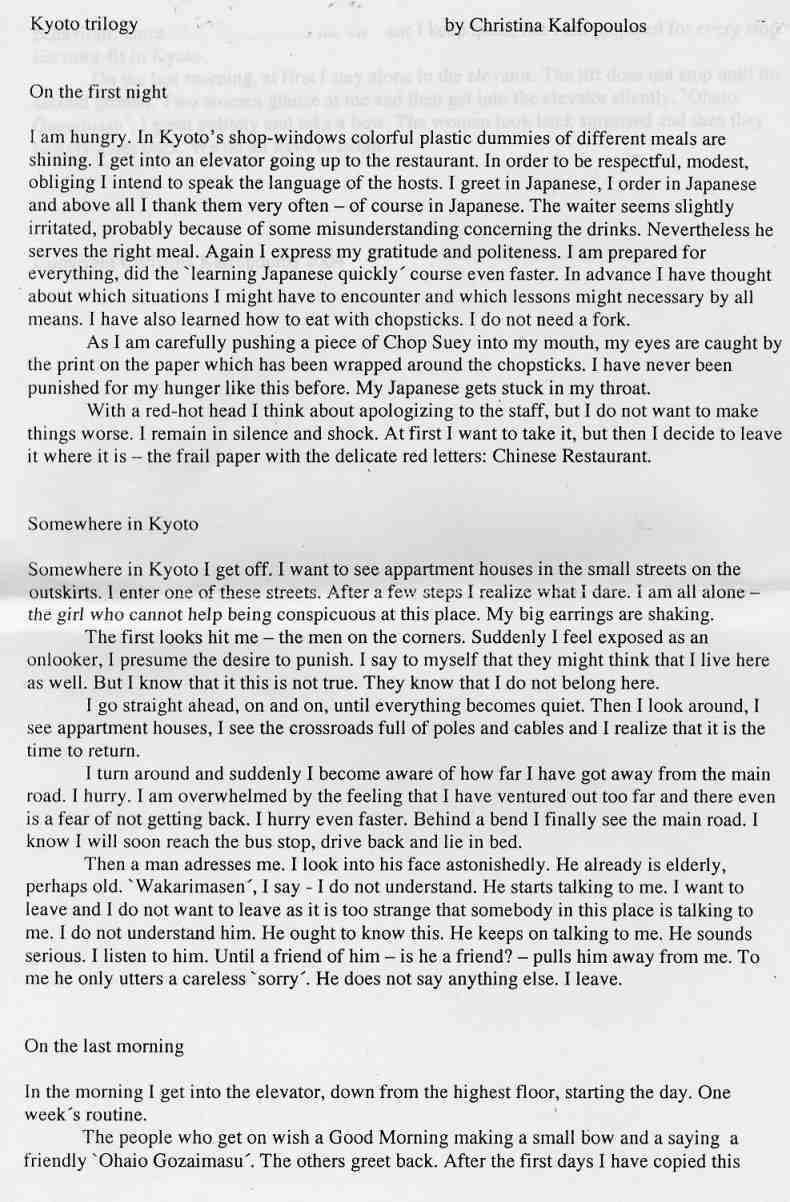
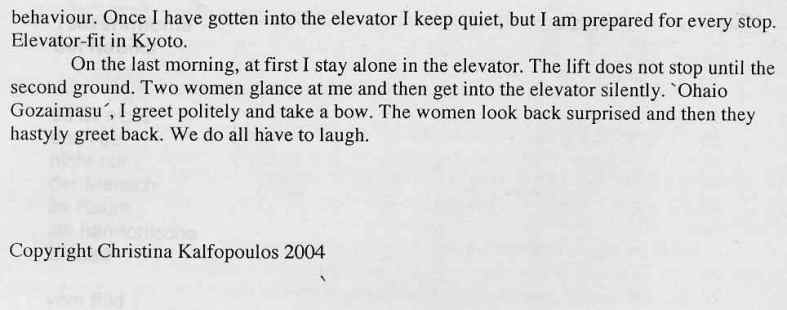
京都(三部作)
クリスチナ・カルフォポロス
(薬師川虹一 訳)
最初の夜
お腹が空いている。京都のお店のウインドウには一風変わった食べ物が色鮮やかなプラスチックの作り物になって輝いている。私はエレベーターに乗ってレストランへ上がる。礼儀正しく、上品に、丁重に、私は迎えてくれる人たちの言葉を喋るつもりなのだ。私は日本語で挨拶する、日本語で注文する、そして何度も何度も日本語で感謝の言葉を述べる。ウエイターは少し戸惑った様子であるが、たぶん飲み物がよく判らなかったせいだろう。でも彼はちゃんと注文した食事を運んでくれた。私は感謝の言葉を丁寧に言う。私は『日本語速習コース』を速習以上に早く済ましてきたのだ。前もって,私はどういう状況に出会うか、どういう勉強が必要かを想定していた。お箸での食べ方も覚えてきた。フォークは要らない。私は注意深くチョプ・スイのなかから一切れを挟んで口へ運んだ。そのとき私の目はお箸を包んでいた紙に書かれた文字に釘付けになった。お腹がへったことをこれほど恨んだことはない。私の日本語は喉につかえていた。
頭はかっとなり、どういって謝ろうかと考えた。これ以上事態を悪くしたくはない。黙ってうろたえている事にした。まず最初、私はその紙を持ち去ろうと思った。だけどそのままにしておくことにした。その薄い紙には美しい赤い文字が書いてあった、『中国料理店』。
京都の何処かで
京都のとあるところで私は降りた。少し中心部を外れた小さな通りにあるアパートメントを見たいと思った。で私は何処かの小路に入った。二・三歩歩いたところで、自分がなんて大胆なことをしているのだろうと言うことに気づいた。まったくの一人ぼっちなのだ私は、こういう所では人目に付かざるをえない女の子なのだ。私の大きなイヤリングが震えている。
最初に出会った街角の男たちの目が私を見詰めていた。自分が見世物になって人目に晒されていることにはっと気づいた。私は彼らが私をこの辺に住んでいる人だと思っているかもしれないと自分に言い聞かせた。が、そんなことはありえないと十分判っていた。この辺の者ではない事ぐらい直ぐ判る。
私はどんどん真っ直ぐに進んだ。やがて辺りは静かになった。私はやおら辺りを見回した。アパートが見える、電柱や電線が重なり合う十字路が見える、引き返す潮時だと感じた。
回れ右をしたとき突然メインストリートからとても外れた所まで来ていることに気が付いて愕然となった。慌てた。向こう見ずに遠いところまで来すぎたのだ、帰れないかもしれないと言う恐怖さえ襲ってきた。足早に急いだ。一つの角を曲がったときやっと大通りを見つけた。もう直ぐバス停にたどり着く、乗って帰ってベッドに入れる。
そのとき一人の男が話しかけてきた。おどろいて彼の顔をまじまじと見詰める。かなり年配、おそらく年寄りだろう。「ワカリマセン」と私。判らないのだ。彼は私に話しかけ始める。私は離れたい、が離れたくもない、だって、こんなところで誰かが私に話しかけてくるなんて不思議すぎるじゃない。私には彼の言葉が全くわからない。判ってくれてもよいはずなのに、彼は話し続けている。真剣らしい。一生懸命聞き取ろうとする。やがて彼の友達らしい人が――友達かな?――彼を引っ張って行ってくれた。彼は不躾を詫びているだけなのだ。ほかの事は何も言っていないのだ。私は立ち去った。
最後の朝
朝、私はエレベーターに乗って最上階から降りる。こうして一日が始まるのだ。一週間の日常。
乗り込んでくる人々は良い朝を願い、小腰をかがめて親しげに「お早うございます」と挨拶を交わす。最初の日から私はずっとこういう仕草を真似してきた。エレベーターに乗り込むと私は沈黙しているが止まる度に身構えているのだ。京都でのエレベーター病。
最後の日の朝、エレベーターは止まることなく三階まで降りた。二人の婦人が私をチラッと見て黙って乗り込んできた。「オハヨウ ゴザイマス」私は丁寧にお辞儀をして挨拶した。ご婦人たちは驚いた目を向け、慌てて挨拶を返した。そして思わずみんな笑い出してしまった。
注(薬師川虹一)
一昨年彼女たちが京都へ来たとき、詳しい話は何も聞いていなかった。メールを交換して、彼女たちが京都に着く時刻とホテルを聞いただけだった。お祖父さんがギリシャの出だと言うクリスチナは片言の日本語を話す利発な娘さんだった。これは京都駅の前にある、新阪急ホテルに泊まっていたときの思い出だろう。可愛い女の子の冒険が目に見えるようだ。彼女はケルン市芸術新人賞を受けた新進詩人である。