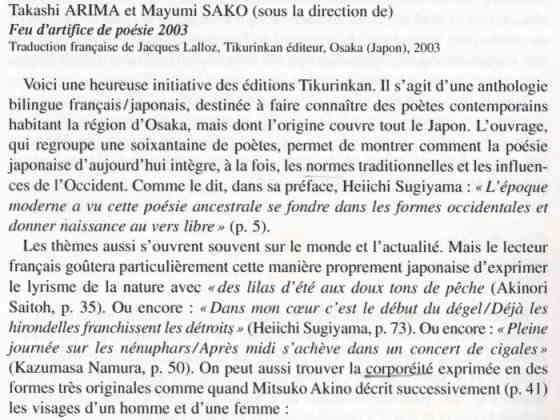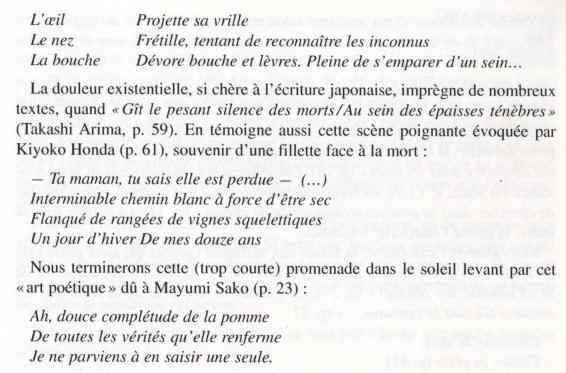「JOINTURE」誌批評 Georges FRIEDENKRAFT氏
日・仏両語によるアンソロジーが竹林館によって出版された。それは、大阪地域に住む現代詩人を紹介するものであるが、その出自は日本全国に及んでいる。作品は60名あまりの詩人によるもので、日本の現代詩がいかなるものであるかを全体として見せてくれるものであり、 同時に、伝統的な規範、また西洋の影響をも提示している。それは序文において杉山平一氏が以下のように述べている通りである。〈近代になって私どもは、その詩歌を欧米の詩の形式に溶かし込んだ自由詩を創りあげてきました。〉
テーマはまたしばしば世界や現代の状況に通じている。しかし、フランス語の本文は特に自然の抒情、まさしく日本的な手法を味あわせてくれるものである。〈やわらかなももいろ 百日紅の〉(斉藤明典)または、〈凍ったこころも溶けはじめた/燕が早くも海峡を越えつつあった〉(杉山平一)、さらに〈睡蓮の真昼/蝉しぐれの夕ぐれ〉(苗村和正)。
私たちはまた、秋野光子が次々と列記して男と女の表情を描写しているように、独創的な形式によって表現された身体性を見いだすことが出来る。〈目 穴を開けるほど見る/鼻 知らない人を知っているかと嗅ぎまわる/口 口も唇も食べる 胸をほおばる・・・〉
また、日本の文学にとって存在することの苦しみは、非常に近しいものとして数多くの詩に浸透している。〈死者たちの重い沈黙がうずくまり/濃い闇が立ちこめている〉(有馬敲)。 もうひとつその例として、本多清子によって呼び起こされた悲痛な次の情景ー死に直面した小さな女の子の思い出ーを挙げておこう。〈お母ちゃんは もうたすからんのや・・・・・・どこまでもつづく白く乾いた道/葡萄の木の骸骨がならんでいた/十二歳の 冬の日〉。
私たちは太陽の登る国の散歩(このあまりにも短い)を、次の左子真由美による《アートポエム》によって終わることにする。〈あゝ 林檎の実のなだらかな完成/そのなかにある真実のひとつさえ/わたしは掴めないでいる〉。
佐古真由美さんが翻訳して下さいました。原文は下の通りです。