 私と詩 杉山平一 私と詩 杉山平一
左の写真は氏にお願いして借り受けスキャナーしました。
堺市ザビエル公園に「安西冬衛の詩碑」
てふてふが一匹だったん(文字が出ない)海峡を渡っていった
を訪ねた時の写真だそうです。
丁度このエッセイを執筆されていた頃です。(永井)
自分がどうして詩人になったのか、わからない。新しい電気技術者の家庭に育った私は家庭で「文学」に接した記憶がない。大阪の北野中学でもそうだった。ただ途中、一年半、東京の麻布中学にいたとき、勝又という先生が、「平家物語」や、志賀直哉の小品を朗読したのに感銘した記憶がある。中村という英語の先生が、自分は白鳥省吾という詩人の弟子だといったこと、矢野という先生が岩波文庫の「ユリシーズ」 の訳者の一人であるということ、陶山という先生に著書があるときいたことなどをおぼえている。とにかく東京の私立中学は面白かった。 の訳者の一人であるということ、陶山という先生に著書があるときいたことなどをおぼえている。とにかく東京の私立中学は面白かった。
数学が得意だったけれども英語はできず、競争率のはげしい理科にはどうしても入りにくく、浪人するのがいやで、松江高等学校の文科へ行った。
家庭をはなれていろいろさびしく気をまぎらわせたいことがあったので、ときどき町の映画館へ行った。それまで殆ど映画を見たことがなく、特に日本映画ははじめて見た。
映画の表現のことを書いたのを見て、モンタージュの面白さなどを知って「芸術」ということを考えてみた。私の好きなのは技術であった。
私は都会そだちだし新しいものが好きで板垣鷹穂の新芸術の紹介などに、山陰の田舎ぐらしのわびしさをまぎらわせた。ノイエ・ザハリヒカイトの建築、飛行機、自動車の写真は、私の心にやきついている。
本屋に部厚い「文学」という本があった。表紙がピカピカ光って、紫と黄色で、古賀春江か、阿部金剛のシュール・レアリズムの絵が描いてあった。めくってみると外国の新しい文学芸術の紹介が、ぎっしりつまっている。色眼鏡をかけたジエイムス・ジヨイスの写真、コクトオの細い手の写冥なども気に入って、買って帰った。それが「詩の評論」がモダニストに占領されて改題された季刊「文学」だった。
そのなかに、津村信夫氏の「小扇」という詩があった。
指呼すれば国境は白い一すぢの流れ
高原を走る夏期電車の窓で
貴女は小さな扇をひらいた。
この小扇をあざやかに配したの三行はモンタージュの面白さだ、この面白さなら自分の知っている世界だ。詩というのはこういうものなのか、とはじめて興味をもった。電車の走るところも気に入った。
後年、やはり詩とは縁のない法科の学生が、私の部屋へ来て、ふと丸山薫氏の詩集から「光」という詩
街燈のアーク橙は
近よると 不意に口を噤んだ
見ないふりして私を遣りすごし
また大声で歌い出した
を読んで、「これならわかる、詩というのはこういうものなのか」といって喜んだのを思い出す。
私は、自分が興味をもつ効果が、詩として認められる効果らしいのを知って大学へ行ってからそれを試してみようと思った。涼しい麦藁帽子をジユラミンの小型飛行機にモンタージュしたものを書いてみた。
「行動」という綜合雑誌が創刊されて、詩を募集しているのを知って、送ってみた。一等が野田宇太郎という人で選外佳作のなかに、私の名があった。詩として認められたらしいことで私は嬉しくなった。
新しいものにかぶれたがった私には、北園克衛氏のエッセイも新鮮だった。コクトオの言葉をもぢった「軽く浮ぶといぅことが大切だ。波紋を描いて重々しく沈むのは沢庵石でこと足りる」という文章などは今でもおぼえている。軽佻浮薄をいばって見せるのが面白かった。西脇順三郎氏の「超現実詩論」もそのころ読んで面白く納得した。
私には詩の仲間というものがない。人と話をすることが、はずかしがりの私にはできないので、私には「投稿」というかたちしかとれなかった。
私は新しい詩の雑誌「マダムブランシエ」というのに詩を送った。ガラスと氷を一しょに噛むというアイデアのものだった。すると鳥羽茂氏からほめて同人に入らないかという手紙がきた。私はそのとき、戸惑いをおばえた。自分に対する漠然とした不安である。いい気になっていいのだろうかという心配で返事を保留した。後年この前衛詩に対する後援者がさびしく亡ったときいて私は大へんかなしかった。
そのころ「四季」が創刊された。佐藤春夫、ラフカデイォ.ハーンなどの原稿やその高度の知的な雰囲気がよく、学友たちが評判している三好、丸山、堀という人々の編集の知的で清潔な感じにひかれた。三好達治氏が選をするから詩を募る、というので、そこへ送ることにきめた。三号に私の投稿詩が出て、「機智を弄する浮薄の手ぶり」ということばがあった。私の漠然たる不安をいいあてられたようだった。私は、そこで、詩を勉強しはじめた。というより技術から心へ興味を移そうと試みた。買えない「測量船」なども学友に借りて来て写した。あとあとになって荻原朔太郎も読んだ。けれど、どこがいいかわからぬまま読んでいた。
室生犀星、島崎藤村など十年位たってからわかるようになってきた。「四季」という異質にぶつかり同調しようとして詩は成長したと思う。はじめて小石川の三好達治氏のお宅へ伺ったとき詩についての無知がはづかしく、何をお話していいのか話題がなくただ先生のおはなしをきいた。その意味をさとるのに十年かかった。いま思っても顔があかくなる。
人生にも悩まず、女の子と話することもできず、恋愛も知らず、草花の名も知らず、電車や汽車のことしか知らずに詩を書いた。後年桐の花を知らず三好達治氏からうかつだねといわれてはづかしかった。
とにかく、私は詩を書いていても、詩に目覚めることが大へんおそかった。詩をかいているのだから、詩をわかろうとして、詩とはどういうものかを知らなくてはと思って勉強した。
私は大器晩成型ではない。都会育ちだから何でも早熟だった。ただ詩だけは、学校時代にも詩人がいたが、向うも相手にせず私も関心をもたなかった。もちようがなかった。
私はながく数年前目覚めるまで「文学」を軽視する風があった。今でも、その気風が少し残っていて、文学かぶれのくせに非文学者風に見えることを気取るくせがある。
「四季」の投稿者の会があり、おそるおそる出席して、はじめて「詩人」という人々を見た。三好、神保、堀、津村氏たちで顔もあげられない気もちだった。そこで立原道造氏を知った。
彼は大学で、私たちの美学の講義を建築科からききに来ていた。ノートを貸したりしたが私もはづかしがりなのであまりものがいえなかった。ある映画館で会ったとき、向うのドアから顔を出してだまって私の方を見ていたりした。「萱草に寄す」や「暁と夕の詩」などリボンで結んで、私の下宿にだまっておいて行つてくれた。私にはとりつくしまのないわからないところが沢山あり、畏敬した。一高出身ということもこわかった。
私が本籍が静岡で、母方が長崎で、学校が松江だというと、東京っ子の彼はいいところばかりだとうらやましがった。
そして彼は旅行に松江に行き、長崎へ行った。最後の旅行だった。
氏がもし生きていたら、詩をかく人のもっている同世代の仲間として、私を誘ってくれたかもしれない。私はついに、詩の仲間というものを持たずに、詩をかいた。
「蜘蛛」創刊号1960年12月20日発行
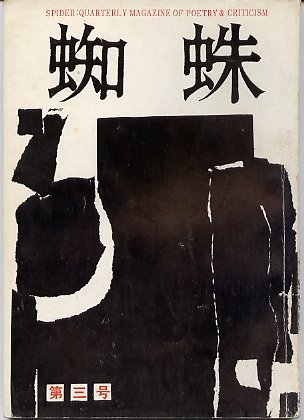
2
先年、近所の娘さんが、道の途中で、私に近ずき、「立原道造さんを御存じだったのですか」といった。そして、私がちょっと識っでいます、詩集を持っていますというと、急に私を見る目の色がかわった。そのことだけで、私までがえらく思われるのである。織田作之助氏と親友だったということだけで、私は随分、えらく見られ、自分自身もそんな気がしたものである。
私は押入れから、立原氏の大きな楽譜型の処女詩集「萱草に寄す」を出してきて、その娘さんに貸した。当時、この詩集を立原氏がリボンで結んで、私の下宿へ届けていてくれたとき、私も大変な光栄に思ったが、たしか百部か百五十部の限定本で、詩壇で評判になどならなかったり立原氏の読者がこんなに増えてきたのは、もちろん死後、而も戦後である。
「四季」に名を出しはじめた立原氏が一高出身者の同人雑誌「未成年」のメンバーなので、私はどんな人なのだろうと、「未成年」の間接の友人を通じて、大学の休み時間に注目していた。工学部の学生だということを「四季」で知っていたので、「未成年」の寺田透とか猪野謙二とか杉浦明平といった人たちが、文学部の事務所の前にたむろしているあたりをいつも注目していた。そのなかに、襟章にTの字のある長身の学生を見つけた。足許を見ると、編上靴の紐がほどけたままになっている。その上等の犬のような感じの細面の人が、立原に違いないと直感した。あとで「四季」の投稿者の会があったとき、私の想像が当っていたことがわかった。
私はその会で、はじめて「詩人」を見た。堀辰雄氏、津村信夫氏、三好達治氏、それに長髪の神保光太郎氏も見えた。
電車や汽車や機械に詩を見つけた私にとって、立原氏の風や小鳥や雲や花や愛についての十四行詩は、なじめにくかったが、本物のわかりにくさがあるようだった。私の心がまだ内面世界に目覚めないとはいえ、芸術の本物というものが、こういうところにあるという畏敬があった。やがてはこんな作品が書けるかもしれないという世界があるが、立原氏のは後者のような気がした。
立原氏は、建築学科の学生だったが、私の属する美学の講義もききにくることがあった。教室の一番うしろの方にときどき顔を見せていた。私のノートを貸したことがあったが、出席のわるい私のノートには空白と落書が多く、はづかしかった。立原氏は建築学科の秀才で、今ときめく丹下建三氏らと同級で、卒業設計では、メダルをもらっている。
本郷の通りで一しょにあるきながら、少しだけ話をしたこともある。私も、ものをいえない方だったが、立原氏もあまりいわなかった。私の「秋晴」という詩のことにふれてくれたことがあった。
「天にハシゴでのぼる詩がありましたね」といった。私は恥ずかしくて、だまってしまって、それきりだったが、何をいおうとしたのか、それきりになった。私の詩は、阪急三宮の長いエスカレータを連想したものだったが、立原氏が梯子といったのを興味深く思った。立原氏がそのとき近く、若い人たちで、詩の雑誌をやるつもりで、そのときは一しょに参加してくれといってくれた「四季」があるのにどうして、また雑誌をつくるのか、と思ったが、私を仲間の一人に数えてくれたのがうれしかった。今でもそれがうれしい。
あるとき、立原氏は、これから堀さんと会うから一しょに行こうといってくれた。神田の支那料理屋で食事をして、銀座の資生堂へ行った。途中、立原氏はある雑誌の詩の特集詩で、自分の稿もふくめて一蹴されている不満を、堀さんにはなしていたのをおぼえている。それから堀さんが「未成年」の編集後記に「心臓に毛が生えている」という杉浦明平氏だかの言葉を、あまりいい言葉ではない、といっておられたことなどを思い出す。
堀さんは「四季」の中心だったから、立原氏と同人の消息などをしておられた。誰それは、家で会わないで、必ず外で会うなどということを。ひどく人みしりする私だったが「四季」の燈下言で、私の投稿詩の評を書いて下さったり「文学界」に紹介して下さったりした三好達治氏を一度お訪ねしょうと思い立った。三好達治、丸山薫の名はすでに高等学校時分文芸部の連中から神様のようにきかされていた。その「測量船」「帆・鴎・ランプ」は、文学界を震撼していた。すでに大学時代の三好達治、中野重治の詩は、当時の文学青年の星であったようである。
小石川の二階家を探し当てたとき表札どころか玄関に、三好達治の名刺が無雑作に貼リつけてあるのを見てちょっとおどろいた。
家の人はお留守で、三好さんが自分で二階に案内された。庭に銀杏の巨木が一本あった。部屋の机には、赤い漢和辞典の縮刷版が一冊のせてあった。(私は、あとで、真似してこの縮刷本を買った)
三好さんの風貌を、村夫子のようにかいている人もいるが、淡泊な感じで、スックと立つという言葉そのままの姿勢であった。詩についての無智をさらけ出すことになりそうで、こわくて何をいっていいかわからずにいた。三好さんは私の気持ちをほぐすように、自分の経験などを話された。私は詩を言葉からでなく、アイデアから発想していたから、詩に使う言葉への劣等感を持っていたので、言葉のことをきいた。三好さんは、きまりがあるわけではないこと、以前、斉藤茂吉が、短歌の中の青痰という言葉をたしなめたことがあることなどを話された。いまゾラの「ナナ」を訳しているが、色々言葉の勉強になる。ボードレールの「悪の華」などは、華麗な言葉を駆使しているようだが、決して語は豊富ではない。言葉の豊富は条件ではないといわれた。名訳の「巴里の憂欝」はもう出ていたころだった。
後年、三好達治氏の「悪の華」は一部、三笠書房から、綴じないまま箱に入れて売り出されたが、
パイプくゆらせつつ断頭台を夢みるもの、おおそはかの 倦怠(アンニュイ)。
などという詩句は今も口をついて出てくる。
そのアンニュイという感じが、今はもう何か色褪せた時代である。
あとで、私は大阪に就職して、一日上京の途中今度は小田原に移られた三好さんをお訪ねした。やはり家族の方は御不在だった。私は勤めの忙しさを洩らした。三好さんは散歩しょうと仰言って着物をきかえながら、「いそがしいというのはうらやましいことだな」と、ふと口ずさまれた。そのときその意味が私にはよくわからなかったが、あとからよく思い出す。きりきり舞いで生きることの幸福を知るには、私はまだ若かった。三好さんは道傍の樹の枝を折って杖にされた。夕暮の小田原の海は、波が高かった。
帰り、すでに暮れそめた小田原の公園を通るときかすかにゆれるブランコに二人の少女が立ったまま「恋って、どんなことか知ってる?」とひそひそ話していたのがきこえた。
その次に三好さんが移られたのも海辺である。
戦時中の私の勤めの疎開先の福井の三国へ、戦後しばらく行っていたが、その宿の近くに三好さんは住んでおられた。
戦いやぶれし国のはて
波浪突堤を没し
と歌われた海を見下ろす丘の上である。九頭竜川の河口で灯台もあった。
かの姿まずしき燈台に、
淡紅のひとみかなしく点じたり
三好さんはその一軒家で、一人、新聞紙の上に真黒に習字の手習いをしたり、訪ねてくる町の青年と話をしておられた。
ある日、そこで、私は三好さんから山本沖子の詩を見せて頂いた。そのやさしいやわらかいすらりとした詩情は、私の詩心を呼びおこした。私は感激して、借りて帰って筆写した。かえって、しばらく私は詩が書きにくかった。福井の小浜の少女である。のちほど、三好さんのお宅に、手伝い代りに滞在していた。おかっばの、少し小ぶとりの、このお嬢さんは、年若いと思って油断しているとぴしゃりと鋭い批評眼で私は、よくやっつけられた。
山本さんが御飯をたいたり、おつけものをつけたりすると、三好さんは、お米でもなすびでも、そのものの味を、生かさねば駄目だといって叱っておられたりした。
三好さんは厳格で、初期の詩「獅子」を思わせる強さ、幸田露伴を推賞される「男性的」な好みの半面、私が路上で貧しい人が助けられたのを見た話をすると、すぐ涙ぐまれるやさしいナィーヴにはびっくりする。
私はそこで泉鏡花の芸術のことや、童詩でサトウハチロウが巧いということや、会津八一の歌や陶渕明の話をきいたり、中野重治氏のため共産党に一票を投じたりされるのを見たりしていた。
「蜘蛛・三号」1961年11月
 3 3
映画評論のことで、キネマ旬報を通じて今村大平氏と仲好しになつた。今村氏は、年長の故もあったが、資本論も読んでいたし世故にも通じていて、私をひきずって、色々なことを教えてくれた。その天才的なものの感じ方、論理の整理の仕方に、今も畏敬の念を禁じ得ないが、彼が映画評論雑誌のことで、北川冬彦氏のところへ私を連れて行ってくれた。
詩のはなしはしなかったけれども、度のきつい眼鏡を紙にひっつけるようにして雑誌の数字を左ぎっちょで書いておられるのを見て、私は、そこにやはり異様な非凡な人物を感じた。そのころ学校で、レオナルド・ダヴインチの講義をきいていたが、あの左ぎっちよの手記を思い出したりした。三度目に、私は一人で訪ねた。雑誌の仕事のことだったと思う。梅酒を出された話し半ばに、北川氏は、私に向い、「杉山君はこのごろ元気にしていますか」といわれ、私は、びっくりして、小さい声で、「私が杉山ですが」といって、恐縮した。すると、北川氏は、しまったというよう顔をして「わぁはははは」と笑い、コップの残りの梅酒をのみ干すと、口から梅の種をポロリと手のひらに出し、それを庭にめがけて、ピューツと投げられた。その印象は今もあざやかである。
私は、そのころ、よく顔がかわっていた、今村氏の世話で、北川氏の詩集や伊丹万作の本を出した京都の第一芸文社が、私の映画評論集を出したいといってきたので、思い切って、私は、その代りあとで詩集を出してくれることを頼んだ。第一芸文社の中塚氏は、私の本を出そうという位だから、商売は下手だったが、良心的で、装幀など、戦時中、もののないときなのに私の無理をきいて非常に苦心してくれた。それが「夜学生」である。
「四季」誌上に北川冬彦氏のこの詩集評が出た。北川氏は南方の報道班から帰られたばかりだった。「杉山平一のこの詩集は、若いのに似ず、完成されていて、的確で、仲々やるなと思って読んでいるうちに、半ばにして、強烈な頭痛におそわれた、これは南方からひきつづきの頭痛にしては、猛烈すぎる。原因はこの本にあるかどうか、わからぬが、途中で読むのをやめる。」というもので、更に、以前、私が織田作之助氏とやった同人雑誌「海風」(夫婦善哉などがのった)にのせた「夜学生」に言及して「『夜学生』というのをどこかの雑誌で読んだときには、杉山平一もくだらない詩をかくようになったものだと思った記憶もあるが」と軽く、詩集の後半にある詠嘆調の詩を、たしなめておられた。抒情を否定するどころか、「私の書くものが詩だ」といった、マックス・ジャコプの翻訳者北川冬彦氏の面目は、見事だと私は思った。
竹中郁氏も、この詩集評のことを、いい批評だねと私にいわれた。幸いに、「夜学生」は「新潮」で菱山修三氏に絶讃されたりして、尼崎の工場街の唯一の本屋で立ち読みして身体がふるえた。中原中也賞につづいて最終回の文芸汎論詩集賞を、笹沢美明氏や野長瀬正夫氏と共に頂いたのも思い出である。
織田作之助氏らが中心になって、丁度同じ頃出た小野十三郎氏の「風景詩抄」と一しょに、出版記念会をやってやろうということで、北浜の河畔のレストランで行なわれた。十人余りだったと思う。ここで、藤沢恒夫氏が小野十三郎氏の詩を評して「小野メガネ」という言葉を使ってその独特の見方を批評された。
席上、藤沢恒夫氏と伊東静雄氏が、何か古今集の作者のことかなんか国文の解釈をめぐつて論争された。両者とも顔青ざめる感じで一歩もゆずらず、私はハラハラしたが、両氏の狷介な性格があざやかで、内容は忘れてしまったが清爽な記憶がある。朔太郎全集の解釈をめぐつて、三好達治氏と室生犀星氏が、つかみかからんばかりの喧嘩になったとか、いう風な「ここに詩人あり」という伝説は、私のような妥協人士には宝石のように輝やいて見える。
伊東静雄氏はそのときパリッとした背広をきておられた。しかし、勤先の大阪住吉中学では「乞食」というアダ名だったという。小野十三郎氏が、詩の話か何かで、住吉中学に招かれたとき、伊東氏が小野氏を生徒に紹介されたらしい。生徒を前にしての、伊東氏の音吐朗々、その生徒にのみこませる説明の堂に入っていることに、小野氏は「びっくりしてもた」と話しておられた。
ときたま会でお会いした伊東氏は、言葉下手な、あまりしゃべらぬ方だからである。ところが、ときたま、私などとすれちがいざま「あなたの『よもぎ摘み』という詩はよかったですね、あなたのいつものかしこぶった奴よりは」とにやりとして向うへ行ってしまわれる。私はドキッとした。私は知的な、インテリジャンスを人にも認められ自分の詩の自慢にもしていたからである。なるはど、「かしこぶって」見えることはつまらんことだなと思う。そして帰って、京都の同人雑誌にたのまれて、調子をかるくかいたつもりのよもぎ摘みという詩を読み直す。二年も三年も良人の復員を待つ女が、昼食のため線路わきのよもぎを摘みに出て、蛇を避けた拍子に電車にふれて死ぬ、家では子供が三人、絵本をひろげて昼食を待っている、という詩であった。
詩の朗読会があって、高見順氏がきたとき、伊東氏は高見氏を見て、「あんなキレイな顔をしていて、どうしてあんなキタナイことを書くんだろう」といったのもおほえている。「小説は何年も長いこと書き続けているとつまらん奴でもいつのまにかうまくなるが、詩はダメな奴は、何年書いてもダメだな」など、私のきく片言隻句にはいつもドキッとさせられる。むき出しの真実しかいわれないからである。親近していた人は、ずい分いろんな箴言をきいていることだろう。
私の散文集「ミラボー橋」を贈ったときはもう病床におられたが、「杉山平一は、二流の山の上にとび上って、バンザイといって喜んでいるようなとこがある」といわれたときいた。おれの書くものが三流か、いま一流といわれているものが一流か、十五年か二十年経って、比べてみてくれといいたかったものの、内心「参ったな」と思った。
私が詩の会に出たりするようになったのは竹中郁氏が引き立てて下さったからである。私は「四季」に育ち、そこに漸く名をつらねるようになったので、私の名を知っている人は「四季」の同人しかない。関西の同人は、竹中郁氏と桑原武夫氏の二人であった。
思い切って手紙して、私は竹中氏と三宮の阪急の駅でお会いした。写真や絵では知っていたが荒い目の麦藁帽子のハイカラな服装が目に泌みた。元町の何とかいうところで、硝子の器に入ったアンコを頂いた。私は「行動」誌上の竹中氏の小説「あいびき」に感銘したことを話した。太い竹を並べた塀の和風のお宅へも伺った。客間の椅子で、「四季」にかいた「邂逅」のことを「あの時間をさかのばって行くのは結構です」といわれて、うれしかった。神戸に空襲のあったあと、竹中氏をお訪ねした。国鉄のなかで私はカントの「プロレゴーメナ」を読んでいた。セピア色の焼跡を窓から見ては、本に目をおとしていたが、須磨駅を出るとうしろから肩をたたくものがある。
「きみはどこへ行く」 「ちょっと知合へ」 「知合の名前は」 「竹中という人です」 「何をする人です」 「詩人です」 「詩人?番地は」というようなことから、私の名前、住所身分をきかれ、とどのつまり、電車で読んでいた本を見せろということになって、はじめて思い当った。「プロレゴーメナ」を「プロレタリヤ」と関係ありと思ったらしい。私の横に特高が坐っていたのだ。カントの説明から詩人竹中氏の説明にまで困惑した。カントといい、詩人といい、まことに説明しにくかった。詩人とは何であろうか。
鈴木享氏は「四季」を論じているなかで(「詩学」)竹中郁氏が「四季」とどうして関係があったのか不可解と書いている。鈴木氏のように最後の「四季」の編集に関係していた人でも、こうなのかと驚いた。戦後の分類で「四季」を四季派という抒情派に整理したため、こういうことになったのである。「四季」は堀辰雄氏を中心とした友人のあつまりで、流派ではなかった。堀辰雄氏の小説「旅の絵」を読むと、堀氏が元町の角のプラジレイロで詩人Tと会うところがある。詩人T即ち竹中氏は象の皮のような外套をきて、そこに現われ、堀氏のために、山手のホテル、エソワイアンを紹介する。ロビイの机の上にはハイネの詩集がある。あの神戸の情緒と竹中氏と堀辰雄氏が私には、切っても切れぬ開係にあるように思われる。ブラジレイロでは声楽家の北沢栄とコンラッドファイトのようなグレーンを見たりしたが灯下管制下の月夜の栄町を窓の大きい神戸の市電にのっていると、イナガキタルホ的神戸が現出した。
創刊以来「四季」の竹中作品に私は非常に感銘をうけていた。「象牙海岸」以後の特に行わけしない作品など多くの傑作は「四季」に発表されている。竹中氏は友人小磯良平氏にたのんで、新制作派の猪熊弦一郎から小松益喜氏の神戸風景のデッサンなどを四季の中表紙にのせて、竹中色は「四季」にみなぎっていた。
竹中氏は、戦時中詩の朗読会などの世話もされ、「青少年のための詩抄」という本があるが、その選択、鑑賞眼に私は多くを教えられた。私はそこで、中川一政の詩を知った。感激して、三好達治氏におききしたことがある。「あれは、犀星を真似たもので」と軽くいわれたが、私はひところ、三郎というびっこの犬に、「よくふとりたるな、ともに写生にゆかずや」という風な詩句を愛誦した。その詩集「野の娘」の色の黒い妹を、いとおしく思う詩や「まづしき母子」が子供に菓子を買ってやれないで「をさなき子よ、よくききわけよかし、なれは父なきもの」とさとされ、幼子は「またおのが野の友にまじらんと走りゆきたり」などに涙して、その影響から逃れられないのにも困った。
これら個性ある選者のアンソロジイは実にたのしい。朔太郎の「昭和詩抄」(富山房文庫)などは傑作だった。そこには朔太郎の現代詩への批評があった。私はそこで・中野重治の「機関車」の「律義者の大男の後姿に、おれら今あつい手をあげる」などを知った。
「四季」のなかで、年齢的にも多少近いので、田中克己氏の作品が好きだった。ハレー彗星が現われたのが千九百十年で、今度、現われるのが千九八六年だから、会えないだろうと「おれの知己はおれの死後に出てくるのだ」と数字を並べるところや「西康省」という二百行くらいの詩でも、牛が何千何百何十頭いて歳出が何十万何千何百元という風にたたみかけて行くところ、歌わないで突放なすシニックな目や選集巻頭の写真に自分のうしろ向き姿を出す(山雅房)など、これこそ自分たちの世代の詩と思った。「コギト」の田中克己氏から詩を求められたときは、本当にうれしかった「帽子」という詩はそのときに出来たのである。そのコギトの後記で、田中氏は「かねて尊敬する竹中郁氏の作品を頂いたのは光栄である」と書いていた。田中氏は多分に竹中氏のおさえた詩法を学んだのであろう。
萩原朔太郎氏を中心とする「四季」の若い人のパノンスの会に一回出席したがそのとき針金のように細い田中氏を見た。
戦後、戦争で散り散りになった詩人を、毎日新聞にいた井上靖氏が中心になって、会をつくってあつめたことがある。そのとき、会なかばに、チラッと田中克己氏が現われ、伊東静雄氏と話して出ていった。井上靖氏に、私は、田中克己が来ましたよ、と告げると、井上氏はすでに知っていて、「詩人現わるという感じですね」と、ぽつりといった。
丸山薫氏も「四季」で私の尊敬おくあたわぬ詩人だった。私は召集解除になったあと、三省堂から出た「革新」の編集を手伝っていたが、そのとき、原稿を頂きに参上した。詩のように、あまりものをいわれない、私は小説を依頼した。あの「貨車」という散文詩がたまらなく好きだったからである。あの旅愁、郷愁、物象からにじんでくる悲哀の世界は「砲塁」以来一時代を画している。それは空しきイメージを呼んで私など、それから抜けることができない。
桑原武夫氏は、丸山氏が商船学校を受験したとき、口頭試問で、「ときどき海や船に夢のようにあこがれてくるものがあるが、それだったら、やめたがよい」といわれよった、と話しておられた。「帆ランプ鴎」は尚我々を誘う。見果てぬ夢はまた丸山氏の世界である。一たび夢やぶれた丸山氏は戦時中、再び遠洋航海に出ておられる。
ちがった意味で、見果てぬ夢は、安西冬衛氏を誘っている。大阪の戎橋にあった十二段家書房で竹中氏にはじめて紹介された。北川冬彦氏が安西冬衛氏の詩のなかの字のピンは、安西氏の隻脚からくると書いてをられたので、片足の方かと思っていた。意外に渋いものわかりのいい人だったが一たび、ロをひらくと、軍艦阿蘇が全速力で下関海峡を抜けて行く話などが出てきて、安西世界が忽ち現出するのが実にたのしかった。
小野十三郎氏も、織田作之助氏との「大阪文学」で親しくさせてもらい、織田のすすめで「大阪文学」に小野十三郎論や安西冬衛論を書いた。今でも、それらは少し自信がある。
1961年7月1日蜘蛛第4号
 4 4
詩集「夜学生」を出したとき、自己嫌悪の一種の変型としての詩人ぎらいから、詩人以外の人に多く贈った。
横光利一氏から「菜の花の茎めでたけれ夜学生」という句につけてトンボの羽根のように透明な哀愁をほめた手紙をもらって喜んだりした。
「善の研究」や「思索と体験」を文学として読んで感激していた私は、西田幾多郎博士にも贈った。私の「黒板」という詩は、
|
自分は眼を閉じる、まっ暗なその神の黒板を前にして、自分は熱心な生徒でありたい、何ごとも識り分けること尠く、生きることに対し、またも自分は質問の手をあげる。 |
というのだが、これは西田博士が、私は半生を黒板に向い、学生は黒板を背にして過した、という風なことを書いておられたことから多分に思いついたのだった。
西田博士から「なかなか面白いようです」というお便りがきたときは、びっくりした。この「識り分けること尠く」というのは、当時の哲学かぶれのためだが、島根大学の雑誌で、森敦教授が、「識」という字を使ったのを学生にほめておられたのを読んだのもうれしかった。
そんななかで、美術評論を書いておられた土方定一氏から「判りすぎて困った」という手紙を頂いた。
私は、勿論そこに皮肉は感じたが、ほめて貰ったのだと思っていた。詩は判りにくいということは、その当時も一般にいわれていたし、詩の判り難さについて、という標題の文章は新聞雑誌にもよく出ていた。今も同じである。
私は、判りにくいというのは、頭のわるい証拠だと思っていた。校友会雑誌の学生の論文のむつかしさは、書いている本人がよくわかっていないからである。若い人ほどむつかしいことをかく。わかり難いのは、詩人が青っぽく、頭がわるいからだ。おれの詩は、浅いからわかり易いのではない。わかったことしか書かないからだ、という風な自負もあった。「夜学生」に「橋の上」という詩がある。
橋の上に立って
深い深い谷川を見おろす
何かおとしてみたくなる
小石を蹴ると
スーッと
小さくなって行って
小さな波紋をえがいて
ゴボンと音がきこえてくる
繋がった……
そんな気持ちで吻とする
人間は孤独だから。
中学生毎日新聞の詩の選をしていたとき、私のこの詩が投稿されてきた。子供の教科書か何かに、出ていたにちがいないと思った。盗作してきている本人にきくのも妙なので、そのままになったが、私の詩は、子供にもわかるのだ。と思ううちに、子供向きなのではないかということにも思い当たってきた。
この詩の最後の一行が、不要であり、不用意な一行であることは、当時、竹中郁氏からも教えられた。それなのに、私は、この一行がいいたくて、書いたようなものだった。説明し尽くしてしまう。一切のあいまいを残せない。それが、自分の大きな欠点であることに、私は年月と共に、気づいてきた。
土方定一氏の「判りすぎて困った」という手紙は、糾弾であることに漸く気がついたのだった。
私は一冊の詩集「夜学生」を持つことを誇りとしていたが、名詩集全集にものらず、詩人選集にものらないわけがわかってきた。むかし、三好達治氏は、若年の私に、リーべに呼びかけるかたちが、一番純粋なかたちでしょう、といわれた。私には一篇の恋愛詩もない。愛の詩集や抒情詩集に、私の名がのる筈もない。神西清氏は「四季」ではあたりにそぐわず窮屈そうだったが詩集のなかでのびのびとしているといわれた。しかし、少年少女向きの詩集にも、採用されないことを知って、私は、自分の判り易さの問いを悟った。
ボードレールは「酔っていなければならない」といった。詩人は「狂っていなければならない」のである。
新進小説家が「一天にわかに晴れ上かり」とか「清貧洗うが如し」とか「神出奇抜」という言葉を使ったと笑われているが、一寸見ては気づかないこういう間違いは面白くない。けれども、金魚鉢の目方は、金魚が死んで沈むと重くなるとか、いうのは間違いで、目方は変わらないのが正しいというとき、正しいことの方が面白くない。月が私についてくる。家に入ったらどうするのだろう、と子供がいう実感にこそ、正しさがある。月はうごかないという正しさには詩はない。詩は「間違がっていなければならない」のだ。
私は日常、労務者と暮しているが、ニキビをニクビという者がいた。子供が生れるのを生産といった。物ができるのが生産で、子供が生まれるのが出産だというような正しさこそ、実感からは間違っている。外国婦人が切符売場で、「コドモ三ビキ下サイ」という。その言葉の間違いの素晴らしさにこそ、詩はある。
日常に退屈して、日常からはみ出そうとするところに、やくざ者がいる。彼らは、正しい言葉と秩序のかびくささに耐えられないのだ。場所をショバとひっくりかえしたり、警察をサツと切り捨てたりする。種をネタといわねばならぬ正しさへの恥かしさの極まったところに詩はある。その極まったところにシュールレアリズムの新鮮がある。間違いと誤解と狂気と異常に詩はあるのであろう。
勝本清一郎氏は、大衆文学と、純文学は、正常と異常のちがいに置いて、純文学の運命を、異常追求の果てに予見しているが、詩にはもともと、正常の坐る場所はない。
私は、白分の判り易さと詩の対決の壁にぶつかった。
そして、また、当時、桑原武夫氏から「温雅にすぎる」というお便りを頂いた。それもまた、自分の性格の壁であった。
詩をつくることで、自分を作って行けると思ったが、次第に自分がわかってくることはかなしいことだった。
(蜘蛛五号)
5
詩を書きながら、私は映画の批評を書きつづけた。キネマ旬報の寄書欄に投稿して以来、戦中も戦後も、色々な縁があって新聞の批評まで引きうけるようになった。批評が甘くなったという非難も知らぬではなかったが、 私は、ほめる批評をかくときしか興がのらぬ自分自身に気づき、批評が自分の吐露であり、また観客のための解説である役割にも気付いて、自分なりの意見をもって書いた。 私は、ほめる批評をかくときしか興がのらぬ自分自身に気づき、批評が自分の吐露であり、また観客のための解説である役割にも気付いて、自分なりの意見をもって書いた。
詩人というものは、小説家よりも批評家に近い。詩にはそういう批評の性格がある。ところが、詩と映画の関係を、他人から問われたり、詩と映画の話をしてくれとたのまれて、私は、戸まどった。詩と映画とは何の関係もない。しからば、私のなかに、どうして一緒に住み込んでいるのか、私はしばしば私自身に問うた。
大先輩として北川冬彦氏がおられる。北川氏が早くからキネマ旬報で批評をかかれたのは、飯島正氏らの学友関係で、生活のためだった。内的必然があったのだとは思わなかった。また、私は、心酔した山中貞雄監督の作品を、北川氏が高く評価されないことから、北川氏の批評はあまり好きでなかった。北川氏はたしかに映画ファン上りの批評家ではなかった。その面白さが、当時の私にはわからなかった。(今でも、私は、技術をぬきにした局外者の映画批評を好かない)
北川氏は島津保次郎監督と大論争したり、このごろの紳士ぶった映画批評家とちがって、再度ならず誌上の喧嘩の矢面に立っておられた。そのなかの収獲に、散文映画論というのがあった。これは、アランの散文論を踏まえたものだが、この論拠に立って、北川氏は山中貞雄を否定し、伊丹万作を引き上げられた。新進として賞讃を博している山中貞雄映画の流れるリズムを否定し、伊丹万作映画のポキポキと折れるような展開にこそ、本物はあるのだと見抜かれたのだ。つまりいえば、これは、北川氏の詩論であったわけだ。詩のリズム、韻文の否定であったのだ。伊丹万作の再評価が行なわれているが、私は今にして、北川氏を秀れた映画批評家だと思う。最近もキネマ旬報誌上で北川氏は新進監督に真向うから喰ってかかっておられた。
私は、詩人北川氏と映画の結びつきについて考えた。映画批評を書かざるを得ない必然はあるのかと。「巨大であること、それは凡そ悪である」とか「どいつも、こいつも泡をふいている、どうしたてんだ! 何だ何だ、何が始まろうてんだ。」の詩人と映画は関係はない。しかしそれ以前『検温器と花』を見ると、はっきりはじめ北川冬彦が、鋭いカメラであったことがわかった。
「落日が、ハイジャンプする少女の楽器のような腰部にぱーんと照り返って落ちた。」
あるいは
「女子八百米リレーの彼女は第三コーナーでぽとりと倒れた 落花」
というような一瞬の視覚、
そして「ビルディングのてっペんから見おろすと、電車、自動車、人間がうごめいている。眼玉が、地べたにひっつきそうだ。」の「瞰下景」の眼玉、それはカメラであり、カメラのズームレンズだ。北川氏にはたしかに映画を語る資格があるとさとった。
私はどうなのか。私が映画に興味をもつ深部をさぐって何年にかなる。
私が詩よりも、散文に、自分の思いのままが書けるような気になって書いた小説集『ミラボー橋』を出したとき、図書新聞は、映画批評家で詩人ということで、北川氏に書評をたのんだらしかった。北川氏は私が小粒であることを指摘されたあと、(伊東静雄氏が私に会ったとき、貴方はもっと小さい人だと思っていました」といわれた)更に北川氏は『ミラボー橋』にはモンタージュがあるといわれた。私が映画評をかいているので、こんなことを書かれたような気がしたが、何年か経って考えてみると、結局のところ私は映画の(画面の断ち切り、組み合せの)性質に内部が魅入られていることに気がつき出した。
モンタージュ論というのは、むかしソヴュトのプドフキン・エイゼンシュタインらの論文によって世界には宣伝されたが、昭和初年、前の市川左団次がモスクワへ歌舞伎を持って行ったとき、時めくエイゼンシュタインが、歌舞伎にモンタージュがある、といって日本の映画青年を驚かせた。
つまり、同時にうごく手や足や首の動きを分解して、手を動かし、次に首を動かす、というような演技をするのは、映画が「分析のモンタージュ」として考えていたことだ。一瞬のできごとを数秒に引き伸ばしたり、時間を止める「見得」の場面など、映画の叙述が考えついたことが、歌舞伎にすでにあったのにエイゼンシュタインは驚いたのだ。彼は更に泪や吠という字にすらモンタージュがあるといって日本文化にうち込む論文も書いている。
エイゼンシュタインの名を更に高からしめたのは、彼の「衝撃のモンタージュ」という考えであった。当時のソ連政府の唯物弁証法理論にあてはめようとして、画面と画面は、正、反、合のように、ぶつかり合って成り立つものだといった。歌舞伎の雪の舞台で三角の紙の雪が天井からおちてくる。しんしんとした雪の夜更の感じを現わすのに、下座音楽の大太鼓の音がどんどんと鳴り出す。針のおちる音もきこえない静寂感を出すために、大太鼓の連打をぶっつける工夫はすばらしい。画面と画面、画面と音が衝突して、新しいものを作りあげてゆく、これこそがモンタージュの神髄であるというのがエイゼンシュタインの主張だった。
「衝突のモンタージュ」は、しかし、ながく私のあたまに残っている。西脇順三郎氏の文章は日本語になっていないようなたどたどしさとわかりにくさの面白さがあって、詩もそこに根を発した生得のものに見えるが、あの「超現実主義詩論」は、よくわかった。そのなかの、結びつくイメージは遠ければ遠いほど、美になるというテーマは、私のむねにこびりついている。その方法は次第に一般化して映画の題名は「純白の夜」が出ても大衆は何となく面白さがわかって怪しまなくなっている。
エイゼンシュタインが「衝突のモンタージュ」といっていたものが、イメージの遠い結合という表現の根本を突いていたことに、近頃、私は思い当る。詩もまたモンタージュである。語と語と、行と行の断ち切り、結合ぶっかり合いである。私はそんなところから、私のなかの、映画と詩を結びつけてみた。
(蜘蛛六号より)
6
真夜中に 格納庫を出た飛行船は
ひとしきり咳をして 薔薇の花ほど血を吐いて
梶井君 君はそのまま昇天した
この三好達治氏の「首途」という詩の、夜明けへかけて夜空に出動して行く飛行船のイメージは好きであっ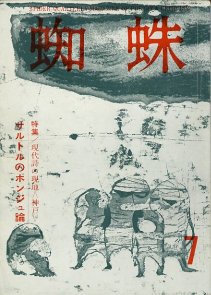 た。「ひとしきり咳をして、薔薇の花ほど血を吐いて」という言葉が飛行船に結びつくのは、飛行船が浮上するとき、砂を吐き出すという事実を背景としていあるからだ、それを知らなければこの詩はわからないと私は友だちに云った。友だちはみな失笑した。私の自然科学的な好みや論理づけは、詩と無関係だといわれた。詩はもっとデモニーシュなものだと。 た。「ひとしきり咳をして、薔薇の花ほど血を吐いて」という言葉が飛行船に結びつくのは、飛行船が浮上するとき、砂を吐き出すという事実を背景としていあるからだ、それを知らなければこの詩はわからないと私は友だちに云った。友だちはみな失笑した。私の自然科学的な好みや論理づけは、詩と無関係だといわれた。詩はもっとデモニーシュなものだと。
それを自分で感ずるのに何年もかかった。
『四季』の十三号(昭和十年十二月号)に、掘口大学氏がシュペルヴィエルの「動作」という詩をかかれた。
ひよいと後を向いたあの馬は
かつてまだ誰も見たことのないものを見た
ついで彼はユウカリプスの木影で
また草を食い続けた
馬がそのとき見たものは
人間でも樹木でもなかつた
それはまた牝馬でもなかつた
といつてまた木の葉をうごかしていた
風の形見でもなかつた
それは彼より二万世紀も前に
丁度その時刻に他のある馬が
急にうしろを向いたとき
見たそのものであつた
………………
この詩を見たとき私はびっくりした。馬は何も見たわけではない。そのことを見事にいい当てて見せる。
何げない馬の動作に神秘を見る、その真実感が、はげしく私に訴えた。この反自然科学的な、非論理性を詩と呼ぶらしいことを肌身に感じはじめたのであった。
知的な興味で詩に触れ、明確を愛した私は、詩を書こうとするにつれて、自分自身の矛盾とたたかわねばならなかった。いわゆる詩にするために、私は自分に嘘をつくことをおぼえた。詩をつくるために、いかに自分をまげなければならなかったか。
臆面もなく花や小鳥や愛に触れる立原道造氏などを身近かに見て、機械やモンタージュを喜ぶ自分の詩人としての劣等感が、つよくなってきた。私は詩人ではない、と自覚した。
自分の面白いと感ずるものを訴えるのは散文の方が、ぴったりすることに気づいた。姿勢をまげないで、自分に嘘をつかないで書けるのは、小説だと思った。そして「ミラボー橋」などを書いた。しかし、それは散文詩として扱われたりした。
そして小説として書くためには、「ははは……」というような笑い声をかくような莫迦げた描写をしなければならないのだった。効果をあげるために、やはりおそろしく姿勢をまげねばならないのだった。
好きなものを書いていると、これはよい文章だ、面白い作文だ、しかし、小説ではないといわれた。私はエッセイをかいた。小説をかいた。しかし、いずれも詩だといわれた。私は実生活では、実業にたずさわっていた。私は経済や労働運動や商売について論じた。
「えらそうなことをいうが、きみは結局、詩人以外何ものでもないよ」と、あるとき小野十三郎氏にいわれた。私は、何かしら吻とした。
詩というものは、結局つかみ難いものだが、たしかに「詩人」というものはある。私は結局「詩人」になってしまっていた。詩をかかなくとも「詩人」というものがある。
「詩人」と「小説家」というものがある。大岡昇平氏によると、他人の噂や評価や評判に気を使ったりして詩人にはひどく俗物が多いという。私も自分でもそう思う。これは結局善人が多いということである。笑うとき本気で目から笑う。小説家は笑っていても目は笑ってはいないような、冷たい、いやな人が、秀れた作品をかく。詩人が詩集に自分の写真をのせることを、からかわれているが、詩人は人が善いのである。そして認められないのを気にする佗しさが弧高のように逆に見えたりしてしまう。そのため詩集をおくられた礼を、礼儀的にかく手紙を、無断で同人雑誌に掲載するようなことが慣習的に行なわれている。うっかりお礼の手紙もかけない。ちょっと見ると、チンドン屋のようなたいへんないやらしい俗物根性に見えるが、そういう、お人好しのなまの感情の露出こそ、詩人の心情なのである。
「小説家」は、冷静である。悪い人である。
小説をかいてみるとわかるが、詩人は短く書く。短いものを好む。本気で笑い泣くから客観ができない。客観をきらうから描写が、まずい。その意味で、私小鋭作家は「詩人」である。エッセイストは「詩人」である。
客観をきらうから、構成ができない。非構成的で、羅列的である。佐藤春夫や室生犀星は、結局「小説家」になり得ていない。しかしその輝きは「詩人」の輝やきである。小鋭のなかに詩があること、詩人であることは、二流と見なされる。「文学」の主導権は、丹羽文雄などのような詩のない非詩人の「小説家」に握られている。
たとえばヘルマン・ヘッセや、シュトルムやリルケやポーは、若い読者を沢山もつが、詩人であることによって文学は二流と見なされている。メルビルは「詩人」だ。そのため「白鯨」は数十年も認められなかった。「天の夕顔」で永く沢山の読者をもつ中河与一氏などは文壇では、そのローマン性の故によそもの扱いにされる。詩人であることが毛嫌いされる。堀辰雄もいつまでも若い読者をもつが、詩人であるから一流の文学者扱いにはされない。
白鳥伝鋭のヤマトタケルノミコトを詩人として論ずることによって若者に鮮烈な衝撃を与えた保田与重郎も、詩人であることによって、嫌われている。
つねに詩的なものは二流である。ショパンやシューベルトは、詩人であることによってバッハのように中心にがっしりと立てない。その作品は小品、繊細、微少である。いや、小品、微少を「詩」と呼んでいるのかもしれない。
絵でも、文学のあるもの、詩のあるもの、たとえば、カリエールマルケ、シャガール、ホドラー、ユトリロなどは、セザンヌ、マチス、ピカソなどに比べて、二流と考えられる。
岡鹿之助や東山魁夷なども「詩人」であることが、その絵画を妨げているであろうか、助けているであろうか。
私の区別の仕方はあいまいであるが、「詩人」であることが、芸術の本質を低めると見るのは、その主観的韻文的な非論理性的なデモニーシュなものが、客観的散文的理性的なものをそこなうと考えられるからである。
詩的なものが、世の中をまだ知らない若い女の学生などに多く読まれれ、感激させているから、それらが二流品とはいえないのは、大衆文学が大人の読みものであるから高いといえないのと同様で、「詩人」の仕事が魂をとらえていることを無視することはできない
我が国のインテリの主流である知的な歴史的なものの掴み方と、「リアリズムへの信仰」が病でないことで、日本ローマン派のデモニーシュな動きはつねに中心になることはなかったが、「詩人」はあまりに、「文学」から疎外されている。
泉鏡花も、小泉八雲も、永井荷風も、太宰治も小林秀雄も、その光彩と生命は「詩人」の光彩と生命であるのは明らかであるが、文学の主導権はまだまだ「小説家」握られている。
女権社会は失われてから久しいが、詩の主導権もまた、そのように失われたままである。
(蜘蛛七号より) |
 私は、ほめる批評をかくときしか興がのらぬ自分自身に気づき、批評が自分の吐露であり、また観客のための解説である役割にも気付いて、自分なりの意見をもって書いた。
私は、ほめる批評をかくときしか興がのらぬ自分自身に気づき、批評が自分の吐露であり、また観客のための解説である役割にも気付いて、自分なりの意見をもって書いた。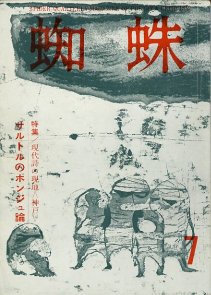 た。「ひとしきり咳をして、薔薇の花ほど血を吐いて」という言葉が飛行船に結びつくのは、飛行船が浮上するとき、砂を吐き出すという事実を背景としていあるからだ、それを知らなければこの詩はわからないと私は友だちに云った。友だちはみな失笑した。私の自然科学的な好みや論理づけは、詩と無関係だといわれた。詩はもっとデモニーシュなものだと。
た。「ひとしきり咳をして、薔薇の花ほど血を吐いて」という言葉が飛行船に結びつくのは、飛行船が浮上するとき、砂を吐き出すという事実を背景としていあるからだ、それを知らなければこの詩はわからないと私は友だちに云った。友だちはみな失笑した。私の自然科学的な好みや論理づけは、詩と無関係だといわれた。詩はもっとデモニーシュなものだと。
 の訳者の一人であるということ、陶山という先生に著書があるときいたことなどをおぼえている。とにかく東京の私立中学は面白かった。
の訳者の一人であるということ、陶山という先生に著書があるときいたことなどをおぼえている。とにかく東京の私立中学は面白かった。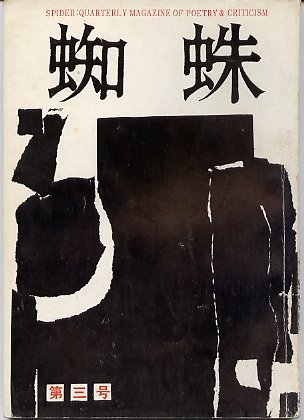
 3
3 4
4